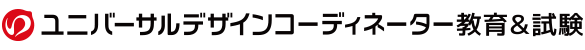「仕事」での優秀なコーディネート
【仕事 】商品選定
準2級UDコーディネーター(小売業)
部署異動により、仕入れや催事企画をする担当となりました。
今までは現場にいて目の前のお客様や商品ディスプレイを見て行動してきましたが、店舗面積が限られている中で、お取引様より新商品の紹介が毎月のようにあり、真新しいものや、お客様のニーズに寄り添う商品を選定できるようにと日々考えます。
今までは、店舗にある商品を接客やディスプレイの工夫で販売する事を考えていましたが、今の部署は取扱う商品が売れるようにとか、催事も売上をつくれるような商材でなければならない等数字ばかりを求めがちでしたが、ある時ミーティングの場で社長に、「部署的には売上を気にする部署だけれど店舗では質の高い接客をして欲しいんだよ、お客様に喜んでいただけることが大事だから、数字で見るのではなく、その時のお客様はどうだったのか、スタッフはどのように接客できていたのかも、フィードバックする事も大事なのだと、企画する自分自身でできることは店舗スタッフとのコミュニケーションを取ることも大事なのだと」企画側の思いを伝えたり現場の声も聴き社内の雰囲気がよくなることで、お客様に選んで頂ける店作りができUDを学んできたこが活かせていると感じれるようにと考えられるようになりました。
那覇空港内にあるお土産屋さんは、どこにでも同じ商品が並べられていて、そのなかで多店舗との違いはUDも学ばせていただいたスタッフが多くいることでUDに基づきディスプレイもおこなってきました。どのお客様にも手に取って頂けるディスプレイ(縦割り)や時代とともにセルフレジ導入も進んでいますが、店舗の通りは車椅子の方にも通れる幅は必須で、店舗レイアウトがどう変わろうと常にUDを意識してきました。今後もお客様と直接携わる機会はなくなりましたが、現場での経験を活かして現場へ足を運ぶ事をおろそかにせずに取り組んで行きます。
【仕事】備品棚の名札付け
準2級UDコーディネーター(福祉)
社内のリネン室は、外部の業者さんも使用します。ある日、清掃後のリネンを片付けていたところ外部のヘルパーさんが来ました。新人さんへの引き継ぎの日だったようで、ベテラン職員が『ここへ返したらいいのよ。同じリネンは同じ物に重ねてね。でも、たまに何もない時があるから困ったらここの施設のスタッフさんに聞いてね。』と冗談めかして説明していました。私も、清掃業務になった当初、クリーニング業者さんが回収後の何もない時に初めて出す(1枚目の)タイミングに当たったことがあります。どこに何が置いてあったかは、前倣えでやっていたためうろ覚え。困った記憶が蘇ってきました。内部の職員も困るのに、週2・3回しか来ない外部の職員さんはもっと困るのではないかと感じました。そこで、棚の壁に物品の名前を書いて貼ることにしました。暗がりでも見えるよう大きな字にしました。壁に貼ったため、重ねてしまえば見えなくなりますが、1枚目を出すときの目印になればいいと思います。まだ他の職員からの感想等を聞いていないので、改善点があれば考えたいと思います。
【仕事】買い物カゴのPOP作成
準2級UDコーディネーター(小売業)
空港では、多くのテナントが入っております。テナントは、それぞれ違う売店になっているため、お会計もそれぞれの売店での会計になります。なかには、売店は全て一緒でお会計はどこの売店でもできると勘違いするお客様もいらっしゃいます。そのため他店舗の商品をレジに持ち込むお客様や、当店の商品を他店舗に持ち込むお客様が増えています。
お客様が当店と他店舗の違いがわかり、スムーズなお会計ができるように考えてみました。
お客様が目に付くように自社の買い物カゴへ、お会計が売店ごとに別であることを表示したPOPを作成し貼り付けすることにいたしました。買い物カゴを利用するお客様は、POP見てお会計がそれぞれ違うことに気づき、少しずつですが効果が出ているように感じます。
今後は、買い物カゴを利用しないお客様にも他店舗の違いがわかるような店舗作りをすすめていきます。
【仕事】返送を求める依頼状への配慮
準1級UDコーディネーター(製造業)
仕事柄、よく書面を作成します。頼まれて、「書類をお送りし、必要な個所に記入して返送していただく」ための依頼状を作成したので、「届いたらすぐに開封し、記入して、返送していただける」ための配慮を試みました。
目標とする返送までの日数は、郵送にかかる日数を考慮して、こちらからの発送後7営業日としました。次に関係者である相手先と私の、共通理解と立場の違い、その違う立場からどう協力を得るか、という点の整理として、その書類が取引上必要な書類であるという共通認識があり、ただし、事務処理上必要なのは私側であるという立場の違いがあり、したがって、相手方への負担を最小限に抑える必要がある、と考えました。依頼状は、書面を一目見て、「記入と返送」という、依頼の趣旨が伝わるよう工夫しました。そこでまず、依頼状のタイトルを、「送り状」等の一般的なタイトルではなく「〇〇記入のお願い」として、タイトルから依頼の趣旨が伝わるようにしました。また、依頼状の右下の隅に、返送先の宛名を記載し、切り取り線を書き入れて返信ラベルとしてお使いいただけるようにしました。2辺を切り離せばラベルになり、細かい紙ごみを減らすことができます。ラベルの大きさは、定形郵便の封筒に収まる大きさとしました。本文には、どの案件なのか、共通理解と依頼内容の明記を心掛けました。
結果、目標の7営業日より1日早く、6日で書類を受け取りました。発送日の記載から、相手先に届いたその日に発送してくださったことがわかりました。日ごろの業務の中でも、工夫できることがあって楽しいと思っています。
【仕事】高齢者への掲示物について
準2級UDコーディネーター(福祉)
5月から現在の会社で勤務をしています。仕事はサービス付き高齢者向け住宅でライフアテンダントという職種です。簡単に言えば、事務や生活相談、施設の維持管理等なんでもやる仕事です。
仕事から様々な掲示物を作成掲示します。一番心がけていることは、掲示物が増えすぎないこと。
高齢者でなくても掲示物が増えすぎると重要度がわかりにくくなってしまいます。大切なお知らせなのか、ただのイベントのお知らせなのか。イベントのお知らせの方が目をひくデザインになりがちで、大切なお知らせはテキストのみの小難しい文章になりがちですので。
次に、気を付けているのが、掲示する位置。自分が勤務するホームはサ高住ですので、お元気な方もいればかなり介護度の高い方もいらっしゃいます。要介護4~5の方はほぼ自室でで寝たきりに近い生活をされてらっしゃいますので、掲示物を目にする機会はほぼありませんが、掲示板がエレベーターの前に設置されていますので、ご家族も目にされます。その一方で車いすで移動をされている方も少なくない状況ですので、掲示物は優先度の高いものほど「低い位置」に掲示していきます。
上記のとおりイベント等目をひき易いデザインのものもありますので、シンプルで目をひき易いものは一番下に。テキストのみのものは、その上に。重要度の低いものは一番上に。
3点目はデザインについて。これはフォントの種類・大きさは当然ですが、掲示物=四角い紙みたいなものですので、「付加情報」については吹き出し等を用いて丸い形状の掲示物にしています。
例えば、移動散髪サービスの案内は四角、当月の実施日は吹き出し。吹き出し部分を毎月張替えます。ものによっては逆になる場合もあります。
【仕事】部署内の情報共有
準2級UDコーディネーター(デザイン)
今までは、部署内の各引継ぎメモや各資料データなどは、年々数も多くなり、探すのが大変だった。
またシュレッダー量の削減、紙のコストダウンによるペーパーレス化の課題もあった。
対策として、紙による各マニュアルを全てデータ化。分散していた各パートの引継ぎメモ(申し送り)を全てアイコン化して閲覧化。それ以外にUDの取り組み方をはじめ、全体周知事項などを文字スクロール化、バナー化にして一目でわかりやすいように、全てHTMLで制作。結果、必要な情報が即時に把握でき、各パート、各マニュアルなど現場スタッフのみならず、各チーフ・リーダー、、管理職まで広く閲覧しやすくなり、意見やアドバイス、問題提起など部署内のコミュニケーションが向上した。今後もさらに改善・改良を重ね、働きやすい職場環境づくりをしていきたい。
【仕事】業務アプリの比較による使いやすさへの気づき
準2級UDコーディネーター(デザイン)
今年度は2級取得のための講座を受講し、誤認誤使用設計学ではミスの分類について学び、直感的利用設計学では使いやすさの分析手法を習得しました。これにより、「なぜミスが起きるのか」や「使いやすさとは何か」を深く理解する基盤ができたと感じています。
業務で現在利用しているアプリと過去に使用していたアプリを比較し、直感的利用の観点から分析を行ったところ、過去に使用していたアプリはアイコンを多用していた点で可視性や対応づけが優れていることがわかりました。一方で、現在のアプリは、システムの仕組みにおいて他のアプリの概念モデルを適用できない点があり、理解しづらく習熟しにくいという課題が明らかになりました。
これにより、今まで漠然と感じていた「使いやすい」「使いにくい」を言語化することができたと感じています。これらの知識をもとに、自分自身の観察力と分析力を高めていきたいと考えています。
今後は「ミス」に着目し、ミスが発生した際にその原因を分類することで、より適切な対応が取れる可能性を模索します。「気をつけよう」「もっと注意しよう」といった曖昧な対策ではなく、具体的に注意すべき点を明確にするミス分類表の作成を目指します。また、これを活用して、過去の業務で発生したミスを分析し、再発防止に役立つツールの開発を進めたいと考えています。
【仕事】食材発注について
2級UDコーディネーター(調理師)
毎月の食材発注にミスが多かったため、職場の作業の見える化について考えた結果、原因は献立表の不備と献立表の使い方にあると思い、肉のカットの仕方や量、魚の数等の必要な情報を全て献立表に記入欄を作り、そこへ載せた。そして、届いた食材を日々の食事ごとに仕分けをした。
それにより誰が見ても食材状態や発注状況がわかるようになり、ミスが減り効率も上がった。
【仕事】通知書とガイドブックのUDリニューアル
準2級UDコーディネーター(デザイン)
毎年発行される通知書と、その見方や必要な手続きについてのガイドブックのデザイン改訂に、今回初めて携わり進行中です。
当初は「年度の違いが分かる程度のリニューアル」という話で、過去のデザインを見ると、色や見せ方の違いはあるものの、内容はほぼ同じです。長年使われているので内容は完成しているのだなと思いましたが、通知書は高齢者や視覚の特性を持つ人に対応していない表現が目立ちます。ガイドブックは一見シンプルにまとまっているようで、通知書とトーンが異なることが気になりました。
また、まわりくどい表現が多く、ユーザーにとって重要な内容(○○の場合は申告する 等)は何行も連なる文章の中に埋もれています。端的でわかりやすい項目もあるのに、突然長話を始めるような項目が混在しているために情報が得にくく、総じて今ひとつなガイドブックになってしまっていることが伺えます。ヒアリングをして、実際にクレームや問い合せが多いこともわかりました。
そこで、改善点の洗い出しから着手して、まずは通知書の視認性を上げることと、ガイドブックは通知書との連動を図りました。まわりくどい表現は文言の再考や、内容ごとに文章を区切る、詳細はスペースの制限がないWEBや電話での問い合わせに誘導する、などの改善をしました。
現段階でも見やすさはアップし、「綺麗なデザインに見えるけど肝心の内容をスルーしてしまう、頭に入ってこない」という状況を脱却できたと思います。実際の使用はこれからなので、ユーザーからのフィードバックが得られるのはかなり先となりますが、社内レビュー等を行い第三者の視点も集めて、より精度の高いツールの完成を目指してまいります。
【仕事】社内のUD推進活動
準2級UDコーディネーター(デザイン)
美術制作会社でグラフィックのアートディレクションを行っています。各部でのUDの取り組みをあわせ、会社全体のUDの取り組みを進めていくため、仲間とともにUD推進ワーキングチームを立ち上げて4年目です。
2023年度はグループワークで自社のUD活動をあらわすフラッグシップモデルづくりに取り組みました。こだわったのは、一般的な「UD」ではなく、自社で働く従業員にとって、また自社の製品・サービスの利用者にとって便利で役に立つものをつくる、ということです。
自分が参加したチームでは、アニメーション作品を「テーマ設定」から、ナレーションなど音まで入れた完成まで、一貫して「UD」をテーマに作るトライアルを行いました。普段はテロップや画像制作など、ビジュアルの一部しか自分たちの会社が携わることはありませんが、今回の企画を通して制作の一連の流れを経験し、映像を作るときにどれだけ多くのチェックポイントがあるのかを洗い出すことができ、様々な発見がありました。例えば、多言語対応にするためにあらかじめテロップのスペースを確保した作画にすることや、作品のテーマ自体も説明なく理解できるようシンプルでわかりやすいものにすること、音の素材も音量をカスタマイズできるように細かく分けてデータ化することなどです。
UD推進活動は、自分たちの仕事のリアルな世界で役立つもの、仕事に直結し効果を実感しやすいものにすることで、社内でも受け入れやすくなると感じています。また、自分たちの専門性を生かして対応することは、クオリティの面で利用者にもプラスになります。次年度も引き続き「自分たちのUDとは」を深く考え行動していきたいと思います。
【仕事】自閉スペクトラム症を持つ自分なりのタスク完遂方法
準2級UDコーディネーター(通信)
私は自閉スペクトラム症です。これは、以下3点の特性を持つ発達障害です。
・非言語コミュニケーションが苦手。
・こだわりが強く、マニュアル通りに動く事を好む。
・曖昧な状況に不安を感じやすい。
私は業務上エクセルを用いたデータ集計作業を行いますが、上記特性が影響し、非常に時間がかかってしまいます。理由として、以下2点が挙げられます。
・エクセル表や計算という非言語情報を処理する事が苦手で、何度もやり直してしまうから。
・ストレスがかかる嫌な作業なので後回しにしてしまうから。
苦手である事に加え、具体的な作業方法が決まっていない曖昧な状況に不安を感じるので、後回しにしてしまう。
そこで、「全体俯瞰と具体化」を意識して、以下の解決策を実行しました。
1.事前に想定される作業内容を想像しながら文章で書く
2.それをマニュアル化する
3.そのマニュアル通りに試しに作業をしてみる
4.上手くいったら、そのマニュアル通りに、本格的に作業に取り掛かる
このように「全体俯瞰と具体化」を意識し、自らが仕事に取り組みやすい環境を構築した結果、これまで4時間ほどかかっていたエクセル作業が。その半分の2時間程で完了できました。
【仕事】建設現場にもUDの考えを!
2級UDコーディネーター
現在は公共工事の発注者という立場で、主に工事安全を指導教育する立場として働いています。建設業界のみならず、全産業において「労働者の高年齢化」が進み、それを起因とする転倒事故が増加しています。また、外国人労働者の参入も著しく、危険を伴う作業にあっては入場前の十分な教育がポイントとなります。
これらは、厚生労働省を中心とする各種団体も重要施策の一つとして考えており、さまざまな取り組みが実行されています。私の勤務する関連工事において、その取り組みをいくつか報告します。
<高年齢労働者対策>
紙ベースの教育資料は、文字フォントを見やすいゴシック体とし、文字サイズも最低でも14ptとする。場内通路には、不陸が少なく、緩やかな勾配がついている場合は、手すりを設置する。仮設足場の入り口や段差部分には、反射材の貼付や照明による足元の明瞭化を図る。
<外国人労働者対策>
なるべく母国語で簡潔に説明し、図や写真を多用した教育資料を準備する。「ニゲロ」「サワルナ」「アケルナ」「ハイルナ」といった簡単な注意単語は、しっかり身につけさせて、確実に行動できるまで訓練を行う。会話を増やし、質問のしやすい雰囲気づくりに努める。
このように、建設現場のUD化は、何も彼らだけでなく、すべての労働者の安全・安心につながるので、今後もその視点・観点を忘れず、引き続き創意工夫をもって取り組んでいきたいと思います。
【仕事】Webアプリシステムのユニバーサルデザイン化
準2級UDコーディネーター(システム開発)
自身の担当しているWebアプリシステムについて、改めてユニバーサルデザインの観点から課題抽出と改善を実施しました。
改めて確認してみると、画像や要素に代替テキストが設定されていなかったり、ページ内のリンクに識別可能なテキストが含まれていなかったり、要素のコントラスト比が足りていなかったりなど、たくさんの改善点が見つかりました。
また、障がいを持ったユーザのアクセスはあまり母数として多くないのかなと考えていたため、アクセシビリティ対応ではページのコンバージョンの向上は見込めないかなと思っていましたが、調査の結果、アクセシビリティの課題が多いページほどコンバージョン率が低くなっているという負の相関があることも分かりました。このことからアクセシビリティの向上は障がいを持ったユーザだけではなく一般ユーザのUI改善にもつながる部分があるのだと感じました。
Webアプリシステムのユニバーサルデザイン化はまだまだ実施途中ですが、これからも取り組みを継続し「すべてのユーザが使いやすいWebアプリシステム」を実現したいと思います。
【仕事】受付での案内表示板の改善
2級UDコーディネーター(デザイン・広告代理)
お客様の社屋受付カウンターに設置している案内表示板の改善を行いました。
受付には案内係はいないので、表示板は総合案内という形で設置してある電話で「○番にお掛けください」というような簡単な案内文で、電話を受けた側がそれぞれに対応していました。
ただ私も訪問する際、アポを取り担当者もわかっている場合は、電話はかけずにその部署まで直接伺っていました。実際、訪問者は電話を掛けたり掛けなかったりの状況のようでした。
これは、訪問者が電話をかける必要があるのか無いのか、判断に迷う表現や内容であること、説明不足が要因であることから、訪問者にどう対応して欲しいかを聞きとり(全ての人が電話をかける必要はない、部署・用件によっては直接行って欲しいなど)、それを表示板に詳細に記載しました。結果、利用者側の判断に委ねることなく、理解しやすい表示板になりました。
また合わせて社内の案内図・経路も表示することで、初めての訪問者・ある程度知っている方に関わらずよりスムーズに案内できるようになりました。電話の受け手側の負担も軽減されました。
改めてUDC視点の大切さを感じたケースでした。
【仕事】研修会の座席配置についてUD的な工夫
2級UDコーディネーター(医療)
職能団体の役員をしており、研修会を主催しております。
座席配置について、当初指定席にしていたのですが、番号を用意する手間があったり、早くに来た方が前方になってしまいクレームを受けたり、知人同士隣になりたい等の要望のため、スタッフの仕事量が増えることがありました。
そのためあらかじめ資料を置いた席を準備し、早く来た順に好きな席に座っていただき、後方を「スタッフ用」と書いた紙を置くことにより前方に空きが出ないよう工夫することにより、クレームもほぼなくなり、スタッフの仕事量も減らすことができました。
【仕事】利用者さんへ提供する珈琲を一目でわかる様にする
2級UDコーディネーター(介護職)
職場である介護施設では毎日おやつの時間があり珈琲を提供しているのですが利用者さんによって砂糖ミルク有や無し、砂糖のみ、ミルクのみや緑茶、ラカント使用などと様々な希望がありました。職員は毎回紙にその事を書いてカップの下に置いていたのですが結構な手間となっていました。
そこでそれぞれの名目をパソコンでプリントアウトしラミネートして使いまわしが出来るようにしました。毎回書く手間が無くなり職員も利用してくれる様になりました。また、ラミネートしていますのでホワイトボードマーカーで利用者さんの名前を記入することも消すこともできてより便利に利用することが出来ています。
【仕事】「見やすい・わかりやすい・読みやすい」だけでない、カタログにおけるUD視点の提案
2級UDコーディネーター(印刷会社(企画制作))
今年度、私は育休から復職いたしました。復職に際し「UDの知見を深めていきたい」と改めて思い、上司に相談をいたしました。そういったこともあり、社内のUD勉強会のメンバーに選出してもらうことができ、「紙媒体におけるUD視点」という内容で、社内のメンバーが担当している制作物について意見交換をしたりしながら勉強することができました。文字の大きさや色の設計というような「見やすさ」に配慮する視認性の視点だけでなく、「読みやすく」「わかりやすい」というような可読性や判読性に配慮した視点に加えて、「伝える」という発信者の一方的な視点ではなく「伝わる」わるための利用者の理解促進を進める情報・仕様・デザイン設計が必要であり、それは最終的に「何をしてもらう・するためのものなのか」という目標設計をしっかり立てることが大切であるということを学びました。この内容を活かし、担当得意先へ「UD視点を取り入れたカタログ改善」として改善点などをまとめた提案を行いました。単に該当する通販カタログの誌面を「見やすい・わかりやすい・読みやすい」のUD視点で変えるのではなく、最終的に利用者が「購入する」ためには何を改善すべきかというのを、利用者に届くカタログ全体を俯瞰して見て、開封~購入までの行動導線にストレスがないかを再確認・設計していこうという内容の提案をすることができました。
【仕事】プライベートブランド商品の包材在庫状況の管理方法について
準2級UDコーディネーター(小売業)
弊社は那覇空港にて店舗運営しており他店舗と差別化を図り、弊社でしか買えない商品開発をしております。
(食品、泡盛、バスソルト、雑貨)
弊社は商品を製造したりパッケージデザインなとのノウハウがない為、商品の中身は製造会社(業者様)へ商品パッケージは印刷業者へ依頼し、弊社のプライベートブランド商品の開発しております。
プライベートブランド商品の包材に関しては、弊社負担しております。
弊社のプライベートブランド商品は20種類ほどあり、パッケージの在庫状況を管理し包材発注のリピートのタイミングを確認し、在庫がなくなる前に発注することで包材の欠品を防ぐことにより販売ロスにならないように在庫管理がとても重要になります。
その為にはいくつか改善を行いました。
- 各業者様へプライベートブランド商品の包材を毎月末に包材棚卸しをして頂く(12業者)
- 業者様にも包材の管理(保管状況)を徹底をお願いする
(双方での確認することで業者様も包材の在庫状況を把握できる) - 毎月、売上実績表を作成し1ヶ月分の全店舗売上数を確認する
- 商品パッケージによってロット発注数が異なるため、各商品のロット数を把握する
- パッケージ発注数は1年間ではける数量で発注する
- パッケージ発注にはリードタイムが1ヶ月~1ヶ月半を要するため、事前に発注する
- パッケージ発注し仕上がった商品によっては保管する場所が異なるためリスト化にして包材在庫の全体を把握する
- 担当者が変更になった場合でも誰でも分かりやすいリスト作成する
【リスト名】- PB商品パッケージ在庫管理表
- PB商品販売実績表
- PB商品包材発注業者及び弊社包材在庫数表
現在リスト作成し活用して包材在庫管理を継続中です。
【仕事】新クライアント
準2級UDコーディネーター(印刷業)
2024年新たに担当したクライアントでは製品作成にどのユーザーにも使用しやすいUD配慮を意識して製品開発にしているとのこと。始めて名刺交換した際にユニバーサルデザインコーディネーター資格が記載されているところを注目され、紙面反映する際にも誰もが見やすい紙面デザインということをするにはどのように配慮すればいいでしょうか?とコミュニケーションの一歩をはかれたことが印象的でした。
【仕事】ホワイトボードに書いてしまった油性マジックペン
準2級UDコーディネーター(教育)
学校にはいろいろなマジックペンが置いてあります。模造紙に書くための油性ペン、ホワイトボードに書くための水性ペン、赤・黒・青・緑など様々です。年に何回か発生するのが、油性ペンでホワイトボードに書いてしまう事件です。当然ホワイトボード用のイレイサーでは消せません。
メーカーさんが対応してくださるのが一番良いと思うのですが、パッと見ただけでは区別が付かないため、未だに事件が発生します。
そこで、大学事務局に掛け合って、4月に配布するペンすべてに「ホワイトボード専用」「ホワイトボード使用不可」というシールを貼ってもらいました。それでだいぶ数は減ったそうです。
ただ、油性ペンの上から水性ペンでなぞるように書くと、ホワイトボード用のイレイサーで消せることが後からわかり、その情報も教員に共有しました。ちょっとしたことですが、意外とウケました。
【仕事】緊急時の受診可能な病院一覧
2級UDコーディネーター(教育、学習支援業)
幼稚園では園児の急な怪我や事故に迅速に対応をしなくてはいけない。重症度によっては1分1秒を争うこともある。以前はかかりつけ医である内科、歯科以外によくある怪我などに対応できるよう皮膚科・歯科・整形外科、総合病院など近くの病院の病院名と電話番号だけが書かれた一覧があり、今この時間はどこが受診可能かすぐに判断がつかない状況だった。その為電話で確認し、休診時間で受け入れてもらえず何か所も電話して時間がかかってしまいすぐに対応できないという問題が発生していた。
その問題解決として縦軸を月曜日から金曜日まで、横軸を幼稚園が開いている9:00~17:30までを1時間単位にした表を作成。可能な時間のところを病院ごとに色別で(病院名と科目)表示。見える化したおかげで休診時間の抜けが明確になった。そこを他の病院で対応できるように穴埋めで救急病院や同科目で受診可能な病院を充てた。また欄外には病院一覧を記載し住所・電話番号・電話時に聞かれる情報や持ち物、病気ごとで聞かれる注意事項も記載。
改良後は曜日と時間から瞬時に対応可能な病院を見つけることができ5分10分かかっていた対応もすぐに対応し連れて行けるようになった。
【仕事】中小企業向けDX推進SaaS商材パッケージの企画
準2級UDコーディネーター(営業企画)
中小企業のDXを促進するためのSaaSパッケージを企画・開発しています。
企画においては、ターゲットのニーズを的確に把握し、サービス内容をわかりやすく提供できるかが重要な課題となっています。
特に、提案書やプロモーション動画といった提案ツールの品質向上に注力し、ユニバーサルデザインの知識を活かすことで、さまざまな年齢層に配慮した設計を実現しました。
〈留意した点〉
・読みやすいフォントと文字サイズ:年配の方でも読みやすいように、視認性の高いフォントや文字サイズを採用。
・情報量の調整:1スライドに載せる文字数を減らし、情報過多によるストレスを軽減。
・視覚的要素の工夫:文字とイラストの比率を2:1とし、視覚的に理解しやすい構成に。
・提案ポイントの絞り込み:提案内容を厳選し、理解しやすく集約。
・利用シーンの改善効果を強調:サービス機能の説明ではなく、実際の利用シーンがどう改善されるかに焦点を当てた表現。
・聴覚的にも理解できる動画作成:視覚的提案書とともに、音声でも理解を促すサービス紹介動画を作成。
・わかりやすさと説明のしやすさの両立:営業担当者向けトークスクリプト等の準備で営業担当者が説明しやすく、お客様が理解しやすい状態を確保。
・営業担当者へのアンケートフォームの活用と改善:提案内容やツールに対する改善要望を収集し、特に効果的だった要素や補足が必要だったポイントを把握。
〈結果〉
顧客提案の理解度が大幅に向上し、売り上げは右肩上がりとなりました。サービス紹介動画の好評を受け、視覚・聴覚の両面から内容を伝える重要性が再認識されました。営業担当者からも提案資料の改善点が寄せられ、これにより今後のツール作成の品質向上が期待できます。今後もユニバーサルデザインの視点を活かし、お客様・営業担当者双方に易しいサービス企画を継続していきたいと思います。
【仕事】アナログで頑張る自分
2級UDコーディネーター(製造業)
歳のせいか自分の抱えている仕事をうまく回せないで残業になってしまうことが最近増えた。もちろん突破的に業務を入れられることも多々あるのですが前はもう少しうまく回せていたのはずなのに・・・
歳のせいでうまく回せないのに、歳のせいで(ベテラン?)仕事量が増えている。信頼して仕事を振ってもらえるので期待に応えたいとは思っているのですが、たまに優先順位を間違えてしまったり、簡単なものを後回しにしすぎて忘れたりと・・・
ちょっとまずいな、と思いどうしたらいいものかとノートにリスト化してみたがそのページがいっぱいになってしまうと次のページに書きこむのだが、終わってない項目も新たなページに書けばよいのだが書き忘れることもあって・・・
この際ちょっとみっともないがモニター周りに付箋を貼りつけていくことにした。付箋に項目と期日を書き込みモニターに張り付ける。納期期日が短い順に貼付け終わったら剥がす。突発的なものが入ったら全部の付箋を見てどこに入れられるか、どの物件を調整できるか考え提出納期を調整し、付箋を貼り直す。
終わった物件の付箋は捨てずに提出日を書き込みノートに貼り付けて見直せるようにした。そのおかげで遅れや忘れが無くなったのはあたり前だが、余裕のある時に簡単なものなどは隙間時間で終えて行けるようになった。
付箋を貼ることで仕事内容の見える化が出来たからだと思う。また付箋を捨てずに取っておくことによりいつ提出した日にちがわかり、同じものを欲しい時にすぐに対応することが出来るようになった。
デジタル重視の世の中ですが私にはまだまだアナログなやり方があっているのだと実感しました。
【仕事】書籍出版(想いを伝える布事-背守刺繍とユニバーサルファッション-)
2級UDコーディネーター(アパレル)
「想いを伝える布事-背守刺繍とユニバーサルファッション-」という本をジツケン様のご協力(引用許諾)の下、共著で出版させて頂きました。私はユニバーサルデザインとユニバーサルファッションについて書かせて頂きました。
ユニバーサルデザインについてはジツケン様に引用許諾を頂き「正しいユニバーサルデザインについての知識」を周知する活動を。ユニバーサルファッションについても「正しい理解」という点で、目に見えるカタチだけではなく、実際の暮らしの中でユニバーサルファッションがどのように役に立つのか、どのような形で暮らしに溶け込んでいくのかを、具体的な事例や解説を用いて説明いています。
事業・実務の中で、アパレル業界への投げかけを継続的に行ってきましたが、業界の理解が全く得られないため、書籍を通じて直接、利用者や潜在ターゲットへ呼び掛けるという戦略を取りました。
概要は以下の通りです。
※高校生にもわかるようにという出版社側から意向を反映し、やさしい文章で紹介しています。
<ユニバーサルデザイン>
・UDの7原則の紹介
・ユニバーサルデザインとバリアフリーの違い
・ユニバーサルデザインは比較級
・側溝のふたと電気のスイッチの事例紹介
<ユニバーサルファッション>
・ユニバーサルファッションとは(概要)
・ユニバーサルファッションの誤解
アパレル業界の安易な行動により、市場に誤った概念モデルを形成されたため、本来あるべき姿を紹介
・ユニバーサルファッションは生きる意欲につながる服
事例を用いて紹介
・今そこにあるユニバーサルファッション
特別な誂えではなく、受け止め方次第で充分ユニバーサルファッションになるということを事例を用いて情報発信(※ユニバーサルデザインの大前提)
・事例紹介
【仕事】オンライン決済を利用した店舗販売について
準1級UDコーディネーター(コンサルタント IT 物販卸業)
コロナ禍環境の後押しもあり、オンライン決済で購入した商品を店舗で受け取るボピス「BOPIS(Buy Online Pick-up In Store)」という、オンライン決済を利用した店舗及びスマートロッカーの商品引き渡し(クリックアンドコレクト Click and Collect)の仕組みを展開、特にその販売する商品在庫の展開方法を工夫し、特許を取得するに至りました。
本仕組みでは購入者側からすると
- 届けてもらうのではなく自分で取りに行くため、送料の負担がない。
- WEBで購入し、店舗に在庫があれば、その日でも取り置きでも自分の好きなタイミングで商品を受け取れる。
- 普段買い商品も、WEBで事前購入しておき、取り置きをするなど在庫の確保ができる。
- WEBで購入することにより店舗滞在や商品を探す時間の短縮ができる。
- 受け取り時に商品を確認し、何か不備があればその場で返品が簡単にできる
一方事業者側からすると
- BOPISの仕組みを導入していないEC事業者との差別化が図れる
- 消費者のメリットを実感して貰えば顧客満足度が高まる
- 来店時に他の商品も見て購入してもらえるついで買いに貢献できる。(ボピス)
- 来店時に、そこでの接客やおすすめの商品を知らせるなどお客様との直接的なコミュニケーションを取るための場として活用できる。(ボピス)
- 店舗に在庫があれば大きく物流が動くこともなく作業工数も削減される(ボピス)
また本仕組みの構築では、多くの個別在庫を持つのではなく、実店舗の在庫を運用することで、空港のみならず、実店舗があるバスや電車などの乗り換え場所であるアクセスポイントでの展開が可能となっています。引き続き UD コーディネーターとして学習したその知見をフルに活用し、問題解決および新しい持続 可能な開発目標に相応しい創造を生み出したいと考えます。
【仕事】クレームからの改善対応(日々の業務の改善)
2級UDコーディネーター(IT関連)
ソフトウェアの操作マニュアルなどはできる限りドキュメントに残すよう心掛けていますが、ドキュメントを読まずに違うことをやり「使い勝手が悪い」「思い通りに動かない」と言う人はどうしてもある一定数存在します。
まずはドキュメントを読ませる工夫を検討しようと思いましたが、それよりもまず操作対象となる側(今回は社内で使う外部ソフトウェア)の使い勝手の改善を試みました。
操作ログが残っているソフトだったので、最初の手順として、誤操作が多い部分を洗い出し、改善対応することにしました。結果、ボタン周りの誤操作が明らかに多かったため、そこを重点的に改善することになりました。
<具体的な改善策>
・ボタンの配置の再検討(記述エラーの回避/思い込みからの回避 など)
・ボタンの文言で紛らわしい文言は変更(破棄、削除のような似たような文言は統一する/変更する など)
・色味の配慮(色分けに頼り過ぎない/見えにくい色の組み合わせは避ける など)
その後、同じ箇所での誤動作はほぼ無くなりました。使い勝手が悪いと言われる部分はあまり変わっていませんが…
次のフェーズとしては、ドキュメントに目を留めさせる仕組みを改善したいと考えています。
【仕事】決済端末の画面上のボタンの枠と文字の配色
準2級UDコーディネーター(メーカー)
お客様からの要望で色覚多様性も考慮した決済端末の画面上のボタンの枠と文字の色を提案してほしいとの要望がありました。
現状の配色は見えにくいように感じるとのご指摘もあり、複数パターン作成しました。
コントラストを測ったところ、感覚的に見えやすそうに感じる新しい提案の配色よりも現状の配色の方が見えやすいことが分かりました。数値を根拠に持つことでお客様も納得し、現状の配色を継続して使用することとしました。
この配色であれば、色の見え方のマジョリティの方もマイノリティの方も見やすくボタンの機能が認識しやすいことを再確認できました。
【仕事】社内UDコーディネーター育成
準2級UDコーディネーター(製造業)
昨年、準2級を取得し、自分自身が知識習得と視野角が広がったことを受けて、次のステップとして社内での定期的なUDコーディネーターのワークショップを開催するプロジェクトを立ち上げ推進。 まずは社内の3級資格保有者から参加者を募り、その中から定員数を選抜。 1年間を1ターンとして月1回、計10回講師を招いてリアルで開催。 このワークショップは、社内のユニバーサルデザイン推進活動の軸となる位置づけとし、知識習得に加えて実際に各自が担当する製品(開発途上のもの)に具体的にどういった配慮ができるかを考え、製品化に落とし込むことを期待している。また参加者にはこの活動が人事評価でプラスとなるように、業務課題に組み入れることが可能とした。
【仕事】多目的トイレの使用中サイン設置について
2級UDコーディネーター(事務職)
職場には各階に多目的トイレがありますが、空いているかどうかはトイレドアの直前位置まで行ってみないとわかりません。多目的トイレは使用頻度が多く、ロフストランドクラッチ杖を両手で操作して漸くトイレに辿り着いた方がトイレの前で数分待たざるを得ない状況がたびたび起こっています。
そこで、多目的トイレの使用中サインを執務室内に取付けてはどうかと検討しています。
ユニバーサル設備は設置すればよいのではなく、実際に誰もがストレスなくまた仕事に差し障りない状況で使用できるようにするようにすることも大切であると痛感しています。
【仕事】忘年会開催について
準2級UDコーディネーター(通信)
私自身、いわゆるコロナ入社世代で入社当初は緊急事態宣言などでここ数年忘年会を実施していませんでした。今年約5年ぶりとなる忘年会開催において約60人規模の忘年会を予定しています。幹事として駅からお店の距離やプラン内容や当日の動きなど決めるところが多く、参加者がスムーズに移動できるように導線を考えるなどユニバーサルデザインコーディネーターの講義で勉強したことが実践できました。
【仕事】アクセシビリティ対応について
準1級UDコーディネーター(デザイン・ブランド)
海外のチームにはディスレクシア(読字障がい)の方がいます。
テレワークで仕事をしている中では全く気づかなかったのですが、アクセシビリティ対応をしている中で判明し実際に意見を聞き、ガイドラインにも反映できました。
見た目では分からなかったのですが、文字組やレイアウトの工夫一つで原則的に読みやすさを高め、ユーザーエクスペリエンスを最適にすることが分かりました。
・すべての見出しや、本文を左揃えにする
・ディスレクシア(読字障がい)や、拡大鏡のように画面を拡大して情報を取得する弱視、シニアの方など、文章がセンタリングの場合、文章があること自体に気づけない場合があります。
左揃えを意識する事で、見た目も奇麗になり大勢の人が便利になります。
アクセシビリティ対応として実施しました。
こういった知識はUDCも基本の考え方であるため、多くの人が現実を知る(体現する)きっかけを作っていく事で社会はどんどん便利になっていく取り組みだと感じています。