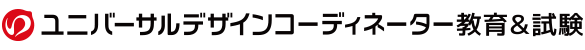「生活」での優秀なコーディネートをご紹介
【生活】怪我で身体が不自由な状態になって改めて気づいたこと
2級UDコーディネーター(デザイン)
ランニングが趣味なのですが、オーバーワークで足の甲を疲労骨折してしまい、1ヶ月ほど松葉杖を使って生活することになりました。
松葉杖を使うのは初めてのことで、診断を受けて歩き方を練習しつつ病院から帰宅したところ、まず玄関のドアを手前に引いて開けることができませんでした。次に玄関から廊下に上がる際に40cmほどの段差が1段あるのですが、それがとてつもなく高い壁のように感じられ、普段はなんてことのない高さのはずなのに、松葉杖の状態だとかなりぐっと力をかけないと段差を上がれないことに気づきました。
段差を登る時のみならず、玄関から外に出るときも段差を降りるときにその高さに恐怖を感じ、また玄関に靴が散らばっていると松葉杖に絡んで転びそうになることが多々ありました。家族にお願いして靴は脱いだら下駄箱にしまってもらうようにして、玄関マットも滑ってしまうこともあり危険だと感じて撤去しました。通勤カバンは両手が使えるようリュックに替え、スリッパのように足を入れられ手を使わず履けるスニーカーを購入して使ってみましたが、かなり重宝しました。
自宅を建てる時に「まだ若いし」「見栄えが良くないし」という理由で手すりをつけなかったのですが、これを激しく後悔しました。
また階段も板の幅が狭く、手すりがあったとしても松葉杖で上がることは不可能だということがわかり、スロープも角度が緩やかで長いものに比べて、角度の急なものはかなり力を入れないと前に進むことができないことがわかりました。
UDコーディネーターの講座でもちゃんと松葉杖や車椅子体験などをしたはずなのに…自分が継続的に不自由な状態に陥って改めて、自動ドアや段差のない空間、UDに配慮された製品の素晴らしさにしみじみとありがたみを感じ、今後の環境空間設計の考えに生かしていきたいと強く思いました。
【生活】衣服のおさがり
準2級UDコーディネーター(小売業)
子供(女の子2)たちが成長するにつれ、当然の様に毎年着なくなる衣服や小物などが出てきてしまいます。成長に伴うものであり、避けては通れない現実でもあります。
解決方法として手っ取り早くリサイクルショップへ持ち込んでいた時期もありましたがまだまだ愛着のある衣服も多く、叩き売りのごとく扱われてしまう現実になんだかもやもや。
まだまだ着られる衣類がどう扱われるかが気になり、実際は売りたい訳ではない事に改めて気づいた瞬間でした。それならば普段からお付き合いのある子育て真っ最中(男の子2・女の子1)のお隣さんに勇気を出して声をかけてみました。
「〇〇さん、まだまだ着られるお洋服があって・・・抵抗なければおさがりですが、活用しませんか」と。予想と不安を裏切り、「えー!めちゃくちゃ嬉しいです!! 本当にいいんですか⁈」と、3人の子供たちが一番喜んで下さり、即座におさがりが成立しました。おさがりは約3~4年前から始めたのですが現在でも毎年、夏・冬の2回を基準に季節に合ったお洋服や部活用品、小物、子供用のリュックサックなどを喜んで活用して貰っています。
おさがりを喜んで頂けるお蔭で、我が家でも洋服やものを大切に扱う習慣が生まれ、次の活躍の場へと衣服を送り出しながら、目に見える形でサスティナブルを実感し、良いご近所付き合いにも繋がっています。
何よりご近所付き合いも減っていく世の中ですが、おさがり文化が繋ぐWinーWinな関係を身近で感じ、また喜んでもらえる様、次のおさがりを準備しつつ、取り組みの意義を感じています。
【生活】両腕にけがをした時に分かったこと
2級UDコーディネーター(主婦)
肘から下にけがをした時の体験です。じっとしていても結構ずきずきと痛くて、力を入れるとさらに痛くなるのでいろいろと困ることがありました。
カバンからお財布を出す時につかんで引っ張り出すのが大変→トートバッグのような口の広いカバンにする→でもお財布をつかむのは避けられない。
食器をスポンジで洗う時にスポンジを持つのは大丈夫でも、食器にスポンジを押し付けるので案外痛い→食器を下に置いてスポンジでこする。
トイレでズボンをおろすのが大変→ウエストにゴムが入ったズボンかスカートにする。
電話の受話器は軽いのに落とさないようにするにはつかまないといけないので痛い→スピーカーで対応。
寝る時に腕が心臓より下になるとずきずき痛い→腕の下にタオルを敷いて体の高さと同じぐらいにした。
痛み止めを飲む時に、錠剤をシートから出すのに力が要り結構痛い→家族に頼んだ→回復後に肘でも押せる、錠剤を取り出すケースを見つけた。
2Lのペットボトルで中央に凹みがあるタイプは指をかけるとあまり力を入れずに持てた。
洗濯ばさみも使うのが怖かったが、一番先を押せばあまり腕に力が入らずに使えた。
予想と違うことがいろいろあり、貴重な体験となった。
【生活】両親の介護を通しての気付き
準2級UDコーディネーター(広告)
親の介護、真っ只中となり、観察と学びの日々です。遠距離住まいだった両親の介護が徐々に必要になり早数年が経ちました。
父はアルツハイマー型認知症、母は身体の衰えが先行し今年他界。現在は高齢者施設のショートステイを長期利用しながら、ほぼ空き家となった実家に通い、父を看ています。
高齢になった両親が日を追う毎に困難な事、できない事が増えていく姿を観察することはもちろんつらいことですが、そんな中でもできない理由は本人でなく家の中に課題があったり、本人が分からなくなり困っているばかりではなく、家族や介護者の声掛けや対応の仕方で困らせている場面も、どんどん見えてくるようになりました。便利なはずの家電の操作に困り、自分の衰えが進行しているのではないかと不安がる様子も多く見られました。
解決してあげられたはずだと悔やんでいることの一つを挙げますと、IHコンロの交換です。
身体の衰えが先行した母は、残存機能で料理をしようにもIHコンロの操作が分からなくなったと嘆いていました。年相応ではありましたが認知症の診断は受けておらず、どこで分からなくなるのか寄り添って見守ってみると、コンロの前を移動するには身体を支える必要があるため、トッププレートのタッチパネルに触れずには動けず、母の意図とは違う操作が行われてしまうことに混乱している状況でした。
掃除に便利で、使いやすさ見やすさのためのトッププレートタッチパネルでも、母にとっては使いにくく不安を覚える仕様だと気付きました。ここでIHコンロの交換を決心していれば、料理上手であった母の自尊感情をここまで傷付けずに済んだかもしれません。
少数派に違いありませんが、もしもこの事例がメーカーの方に届くのであれば、またはIHコンロの買い替えを検討中の方に届くのであれば、この気付きがお役に立てたら幸いです。
【生活】病状変化一覧表の作成
2級UDコーディネーター
眼球使用困難症の日々の症状の変化を、ひと目見てわかるような記録記入シートを作成しました。
今までは、日記にその日あった症状を箇条書きしていました。
しかし、それでは変化がわかりにくい上、目当ての記録文を探すのが大変でした。
記入漏れも多く、日記はかさばるので、持ち運ぶ際荷物になってしまうところも難点でした。
・朝昼晩で症状の変化を数値で記入
・天気
・日中の過ごし方
・出た症状の種類
上記4つの項目に分けて、日にちごとに記入する表を作成しました。
《工夫した点》
1.「記入漏れをなくす為、『丸で囲む』『チェックつける』『穴を埋める』形式のみでシート作成。」
→これにより、記入時の負担と時間の軽減にも成功しました。
2.「月毎にファイリングし、ページにはインデックスをつける。」
→これにより、読みたい日を探すことがスムーズになりました。
3.「それぞれの項目の1番下に、その月の合計(または平均)を記入する欄をつくる。」
→これにより、月の変化も分かるようにしました。
またこれを機に、記録の仕方も見直しました。
今までは、症状が出るたびに手書きでメモしていました。
その為、外出先や手元に筆記用具がなかった際、詳細を忘れてしまうことが度々ありました。
そこで、「スマホに専用のショートカットを作り、症状が出たらそこに音声入力でメモ→後でまとめてシートに記入」という方法に変えました。これにより、症状の記入漏れが減りました。
【生活】食卓に彩りを
2級UDコーディネーター(食品メーカー)
実家で高齢の母親がひとり住まいで、当然、食事もひとりですることになります。
私もひとり住まいなのでわかりますが、自分で作って、ひとりで食事をすると、あっという間に食べ終わってしまい、どうしても味気なく感じてしまいがちです。作るのにも、力が入らなくなる可能性があります。
食事は大切で、しっかりと栄養を摂れるようにしたいと思い、少しでも食事の時間を楽しむために、食卓に“ランチョンマット”を取り入れることを考えました。色・柄の様々な数枚のランチョンを、母親の誕生日にプレゼントし、その日の気分や食事の内容によって使い分けることを提案しました。
ランチョンは、今まで使ったことのないアイテムでしたが、どのように使うものなのかと、興味深々で楽しそうに受け入れてもらえました。今では、自分なりに、「今日はコレ」などと選んで楽しんでいるようです。また、朝食時のパンくずなどが落ちても、簡単に片づけができることにも気づいたとのことで、便利さも感じてもらえました。
自分で、気に入ったものを買ってくるように促しているのですが、まだ、そこまではできないようです。今後は、選ぶ楽しさも感じてもらえることを期待しています。
【生活】お菓子のストック
準2級UDコーディネーター(情報システム)
私はチョコレートやポテチなどお菓子が好きで、お買い物ついでによく購入してしまいます。
もともと、購入することで満足をしてしまうため、すぐに食べることはなく、お菓子のストックがいっぱいになってしまうことが多々ありました。
以前は、会社に持って行って、職場のみんなにおすそ分けをしてそれなりに消費できていたのですが、在宅勤務がメインになり、おすそ分け回数も減り、お菓子のストックがめちゃくちゃ増えていて、このままでは大変なことになってしまうことに気付きました。
そこで下記のことを行ってみました。
- 全体量を把握 ➡ 家にあるお菓子を全部並べてみる(自分で思っていた以上に多くて驚愕。。。)
- 賞味期限を確認 ➡ 賞味期限順に並べ直す(お菓子の賞味期限は意外と短い。)
- お菓子BOXを作成 ➡ 蓋なしのBOXを準備し、種類別/賞味期限順に並べる
- お菓子BOXを確認 ➡ ストックを確認してから、買い物に行くようにする
ストックをすぐ確認できることで、ついつい買いをやめることとストックを減らすことが出来るようになりました。次は、お菓子BOXを小さくできるようにするとともに、日用品のストック削減も行ってみたいと思います。
【生活】自宅マンションの被災時の対応の仕方についての情報共有
準1級UDコーディネーター(不動産賃貸業)
【はじめのアクション】
能登半島地震で始まった2024年。被災した時に自宅マンションの設備は、どう対応したら正解なのかが不明でモヤモヤしていた。管理会社に電話して聞けばすむことではあるけれど、住人がみなその情報を知っていなければ、意味がないと思い、管理組合に、「災害時に想定される情報についての事前共有のお願い」という文書を提出した。
具体的には、以下の2点についてお願いした。
- 私も確認したいことで、それを住人にも共有してもらいたい。
- 例)断水しても、トイレをお風呂の残り湯などで流してよいのか。
- 東日本大震災の1年前に建てられたマンションなので、当時の被害状況をしりたい、など。
- 私は知っているが、知らない人がいることで、他の住人も困ることを共有してもらいたい。
- 例)立体駐車場はたとえ停電が復旧しても、専門業者の点検が終わらないうちは、中の装置や車が破損する恐れがあるから勝手に稼働してはいけない、など。
- 集合住宅では、互いの行動が影響しあうので、同じ情報を伝えることで少しでも二次被害を防ぐために大切だと感じていた。通常は常駐している管理人が、その都度貼り紙をして通知しているので問題はないが、大きな被災になればその対応ができないことも考えられる。
【結果】
理事会で私の意図は理解されたようで、どのような形で情報共有するか検討された。ようやく11月末に管理会社がもともと持っているフォーマットに私が質問したことを加筆する形でオリジナルの「防災のてびき」が配布された。
【反省・考察】
結果として被災時に停電断水になっても、トイレは流してよい、という情報は住人にとどけられたが、肝心のみんなが正しい行動をとることで、被害を最小限にとどめられる、二次被害を防げる、ということを明確に共有することはできなかった。
つまり私が一番モヤモヤしていたことは、「集合住宅の特性を認識した被災時の行動が重要、そのために必要な情報を共有してほしい」ということだった。この認識をはっきり持っていない中で要望書を作成したで求める結果がえられなかったと反省している。
【今後の行動】
次年度の総会で、「防災のてびき」の活用、配布の意図について再確認を促す発言をし、総会議事録にそのことを残すことで、多少でも補う。
【生活】離れて暮らす両親の観察のむずかしさ
準2級UDコーディネーター(メーカー)
今年、ずいぶんと久しぶりに、神奈川から両親の住む山口に帰省しました。コロナ禍に加え、母親が癌を患ったこともあり、約7年ぶりの帰省でした。
その間、ビデオ通話の環境も整え定期的に連絡をとっていたので、「帰省するよりもむしろ顔を見る機会が増えて安心だ」と思っていたのですが、実際に帰省してみると、それだけでは伺い知れない状況を実感しました。
帰省直後の近況報告のような会話では特に違和感を感じませんでしたが、就寝用の布団を母親が用意してくれようとしたとき、(元から同じことを繰り返し話す母親でしたが)、「この布団は誰が持って来たんだっけ?」と認知症のような発言が出てきました。他にも似たようなことが続くため、近所に住む妹に確認したところ、そうではないかと感じて不安になったことはあったが、玄関口での会話ではほとんど変化がなかったので、思い過ごしか、と感じていたとのこと。(癌やコロナのこともあり、家に入る回数は減らしていたとのこと)
「実際に会わないとダメだね」と断ずることは簡単ですが、昨今の“テレワークは悪”の風潮も含め、そこは否定したいと考えています。反省すべきは、コミュニケーションの質ではなかったか、と。認知症等はいつ発症してもおかしくないのだから、念の為 少し探る ぐらいの質問を含んだ会話はできたのではなかったのか、と。
帰省から戻ってすぐ、会話の中にUDC的な視点も含めて、遠隔観察を開始したところです。
【生活】魔の階段
2級UDコーディネーター(デザイン)
うちには魔の階段がある。2階から1階に降りるときに、つい踏み外してしまう階段だ。これには家族みんな困っている。
なぜかというと一番下から2段めのところで、手すりが終わっている。足元を見ずに手すりだけをたよりに降りていくと、最後の階段の存在を忘れてしまい、最後の段を踏み外してしまう。
階段の最後の段に目立つシールを貼るか?という案も出たが、色がダサいうえに、足元をみるという習慣をつけるのも難しい。
そこで採用された案は、同系色で目立たないが凹凸のあるシールだ。2階から降りていき、最後に足裏にボコッとした感覚があれば最後の階段ということになる。
たとえ手一杯に洗濯物を抱えていて足元が全く見えなくても、足裏の感覚を頼りに最後の階段がわかる。今のところうまくいっているので、解決の兆しが見えている。
【生活】ちょこちょこ掃除でそこそこキレイをキープ
準2級UDコーディネーター(書籍の編集)
私は綺麗好きですが面倒くさがりでもあります。毎日の掃除はしますが、ほこり掃除やお風呂掃除などは「毎日はしなくていいか」と思ってしまいます。
その結果、テレビ台の埃がだんだん気になりだすのですが、面倒くさくて放置、でも気になる毎日…やっとスイッチが入って大掃除。ピカピカになるけど、ああ大変だった~の繰り返しでした。
今年はふと「大掃除が嫌なら分割して小掃除にしてみよう」と思いまして。今まで1~2時間かけていたものを「今日はここだけ」と分割して、10日~2週間で1周するようにしました。普段の掃除+ちょこっと。やりすぎない程度。
そうすると、100%キレイにはなりませんが、80%キレイが続くようになり、私のストレスが軽減されました。
今までは「掃除するストレス」<「汚れているストレス」となるまで放置していましたが、ストレスにならない程度の小掃除を続けることで、汚れているストレスを感じない生活になりました。
自分の行動をUDコーディネートして、満足度の高い毎日です♪
【生活】薬の飲み忘れ防止
準2級UDコーディネーター(情報サービス・ソフトウェア)
私自身、毎朝薬を飲んでいるのですが、漢方薬が今年から処方されるようになりました。
漢方薬は「食前」に飲む必要があるのですが、朝は眠かったり忙しかったりするためどうしても飲み忘れてしまい、食事中に気づくことがしばしば。
そこで、前日の夕食後にテーブル上に薬を置いておいて次の日の朝食時に事前に気づけるようにしてみました。しかし、1歳になる娘が勝手に触ったりすることがあり、危険だったためこの対策はやめることにしました。
よくよく考えたら、自分は毎朝必ずコーヒーを入れて飲むので、コーヒーの砂糖とミルクが入っている引き出しに薬を入れておくことにしました。
そうしたら、小さな子供にも気づかれず(いたずらもされず)かならず朝食前に開ける引き出しなので、食前に漢方薬を飲むことに必ず気づき、忘れることがなくなりました。
【生活】冷蔵庫内の整理
2級UDコーディネーター(教育サービス)
高齢の母と二世帯同居中ですが、主人や子供達が休みの日には、一緒に食事をとるなどしています。先日母から「みんなが冷蔵庫内の物を勝手に動かすので、しまったと思っていた場所に物がなくて困る」と小言を言われました。そこで、庫内の中のものが常に定位置にしまえるよう工夫しました。
庫内の棚の高さに合わせた大きさのプラスチック製のカゴやトレーをいくつか購入し、その中に飲み物、調味料、バター、ソースなどを母の使いやすいようグループ分けし、まとめて収納しました。手前から奥に向けて、何が入っているかわかるようにイラストを描き、カゴやトレーの前面にプラスチック製のカードホルダーを貼り付け、その中にイラストを差し込めるようにしてみました。
母の冷蔵庫内は、あまり沢山のものがある訳ではないので、比較的ゆったりと収納されており、確認もしやすいと思うのですが、母には母の拘りもあり、また、奥の方に入っている物が見つけにくいという事もありましたので、トレーやイラストを使って整理する事で、把握しやすくする事ができました。
また、母以外の家族が出し入れする際には、イラスト通りの場所に戻す事を徹底してもらうようにする事で、「どこにしまわれたかわからない」状況を作らないよう注意するよう務めました。
これにより、庫内の整理整頓が簡単にでき、イラストも本来の商品パッケージを真似て作ることにより、直感的に見分けができると喜ばれました。
これから年末年始に向けて、一緒に食卓を囲む機会が増えるので、なるべく母のストレスを増やさないよう、工夫していきたいと思っています。
【生活】時間の有効利用や将来への投資
準2級UDコーディネーター(製造業)
つい休日怠けてしまう癖や、一度考えたアイデアを、時間がたった時に忘れてしまう、そんな私の癖(特性)の中で、将来に向けての焦りがあり、将来に向けて効率的に投資が出来る方法を模索した一年でした。
- 発明家として、日常の些細な不満点を解決するアイデアを、メーカーに売り込んだり、wemakeというコンペに応募したり活動をしています。
- 休日に、休養の時間の延長線上で、つい、やろうとしていたことが進まずに後悔することが多く、仕組みで解決しなければと感じました。
- 取り入れた仕組は
1.カフェの個室を事前予約し、料金の支払いも完了しておく
2.例えば日曜日の15時から1時間は毎週必ずと決めて、誰かに公言する
と言った主に2つを取り入れ、実際の売り込み活動を進めた一年でした。
同時に、想定するターゲットとその効果を動画にし、資料にQRコードを載せることで、企業側に伝わりやすく工夫しました。
→結果、採用とはならなくても、検討頂いたりと、嬉しい話がいくつもありました。
発明は数十種類あり、日々、気付いたことや解決方法をスマホのメモに記し、蓄積しているお陰と思います。今後も、仕組やルールによって、自身の性格や特性をカバーできればと思います。
【生活】日頃の心掛け
2級UDコーディネーター(航空業)
日常のちょっとした行動により、他の人へ与えるストレスや不不快感を軽減させられるのでは、この考え方自体もUDになるのかなと思い、私が心掛けている小さな行動をいくつか紹介します。
- コンビニ等の飲食スペースを利用後は次の人が気持ちよく使えるよう、備え付けのふきんが無くともテーブルと椅子背もたれの上部(人の手に触れる部分)を拭くようにしています。
- 公衆の手洗い場において、自分が使っていない蛇口がきちんと締まっていない事に気付いた時は、その蛇口も締めています。
- 公共のゴミ箱が満タンの場合は、ゴミを持ち帰るようにしています。
- スーパーなどで袋詰めされていない野菜を購入する場合は、備え付けのビニール袋を裏返しにして手にかけ商品を取るようにし、素手で他の食品に触れないようにしています。
- 電車内で自分と周りの人の間にあまり余裕が無い時や、つり革に掴まれない時は携帯を触らないようにしています。
【生活】冷蔵庫の可視化
準2級UDコーディネーター(デザイン)
UD的な考えかたから行動してみました。
平日は共働きのため料理をする時間が取れません。以前は、作り置きした食材などがカビが生えてしまったり失敗を多く経験しました。
そこで有効に食材を食べきる策がないかと検討したところ、冷蔵庫をすべて透明な容器と、量がへったら小さいサイズに移していく。
目に見える容器。場所も目視できる場所のみ置く。という事をルールづけする事により。劇的に改善されました。